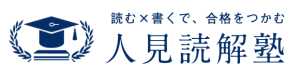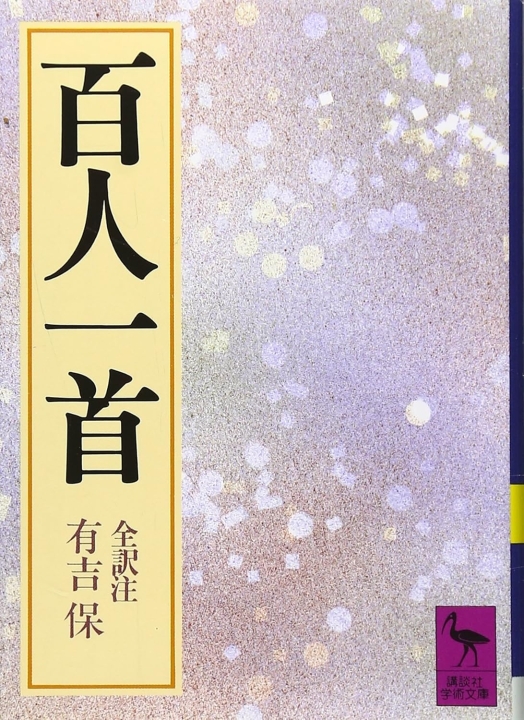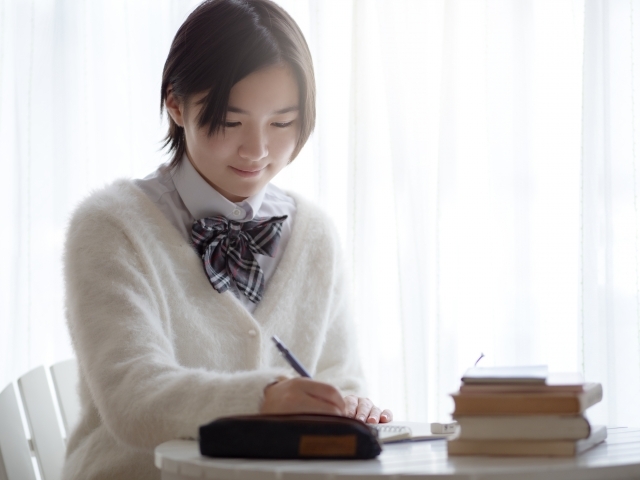「古文=暗号」を情報処理する感覚で読む!
共通テストの古文・漢文は、いまや単なる「読解テスト」ではありません。本質は、「古典の情報処理試験」です。
「古文を読め」とは言われていません。「古文という暗号を、文法という法則をもとに正確に処理せよ」と言われているのです。
つまり、古文や漢文は「文学」ではなく「情報」に変換されているのです。
古典が情報処理の対象になっている――なんとも贅沢な試験だと思いませんか?
① 正答率9割への第一歩は「基礎の徹底」
まず、古文・漢文の基礎は学校の授業の延長線上にあります。共通テスト9割を狙うには、土台である 文法の正確な理解 が不可欠です。
✅ 古文の基礎
助動詞の意味と接続
助詞の機能(特に「を・に・が・は」)
敬語の使い分け
これらをあいまいにしたまま過去問を解いても、思考がブレてしまいます。「主語が誰か」「述語がどこにかかるか」を明確にできるようにすることが第一歩です。
学校の授業では一見地味なこの部分こそが、後の得点を支える“文法的思考の骨格”になります。共通テストでは、まさにこの“基礎の整理力”が問われているのです。
② 傍線部周りの「情報処理」テクニックを磨く
基礎を習得したら、次のステップは 傍線部周辺の処理 です。ここからが「学校では教わらない」領域です。
傍線部は、古文や漢文の「論理の要」です。問題作成者は、傍線を「正解が1つしか存在しえない位置」に置いています。つまり、傍線部の前後に“正解の手がかり”が必ずあるのです。
したがって、9割を取る人は本文をすべて訳すのではなく、傍線部の前後を情報処理のようにスキャンして読みます。
文法的な手がかり・主語の転換・引用表現の有無などを見極め、「この文の主張はどの情報に基づくか」を分析する。これが、共通テストにおける“古文情報処理”の技術です。
③ 「過去問演習」でしか得られない勘
2つ目の誤解は、「文法を覚えたら点が取れる」というものです。実際には、過去問演習でしか見抜けない“設問のパターン” があります。
たとえば――
傍線部の内容を「言い換え」させる問題
登場人物の心理を文脈から判断させる問題
物語と随筆で論理展開の型が異なる問題
こうした形式は、過去問を通してしか体感できません。したがって、共通テスト9割を狙うなら「過去問分析 → 根拠整理 → 再現演習」を繰り返すこと。このプロセスが、9割突破の最短ルートです。
④ 古文を「情報」として読む感覚を身につけよう
私たちは現代文や英語では、自然に情報処理をしています。では、古文になると急に「感覚で読む」人が多いのはなぜでしょう?
共通テストで求められているのは、「古文を感覚で味わう力」ではなく、古文を情報に変換する冷静な処理能力です。
たとえば――
「〜なりけり」という表現があれば、それは「感情の回想」か「発見の驚き」です。「けり」が過去の回想なら文中の主語は固定、発見なら場面が動いている――こうした構文情報が正答の根拠になります。
このように、古文の一文を“論理的に情報化”していく練習をすると、設問で問われる「心情・理由・内容一致」が一瞬で見抜けるようになります。
⑤ 漢文も“構造読解”で9割を狙える
漢文も古文と同様に、構造を読み取る力が決め手です。返り点や句形をただ暗記するのではなく、「なぜこの順で書かれているのか」「論理がどう転換しているのか」を意識しましょう。
たとえば「〜者」「〜也」「〜焉」は、文中で論理的な“骨格”を形成する目印です。これらを構文として読み取ると、漢文の世界が一気にクリアになります。
⑥ まとめ:古文・漢文は“情報処理科目”である
共通テストの古文・漢文で9割を取る人に共通しているのは、文法知識の多さではなく、「古典を情報として扱う冷静な思考」を持っている点です。
つまり、
助動詞・助詞・敬語などの基礎を完璧にする
傍線部周辺の論理構造を情報として処理する
過去問を分析して出題パターンを再現する
この3つを徹底すれば、9割は十分に狙えます。
🎓 最後に:古典を“読める人”より“処理できる人”へ
古文を「味わう」段階から、「処理できる」段階へ。それが共通テスト9割の分かれ目です。
人見読解塾では、古文・漢文を「情報処理の型」として学び、誰でも9割を狙えるように指導しています。
文法を武器に、「情報を見抜く力」を身につけましょう。それが“現代の古典力”です。