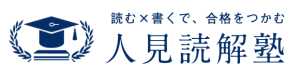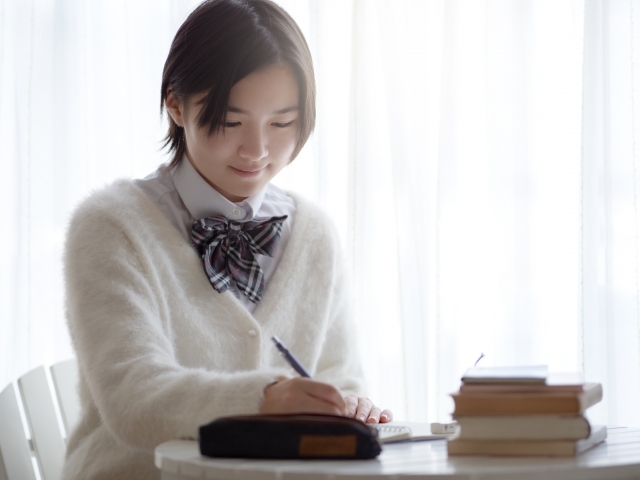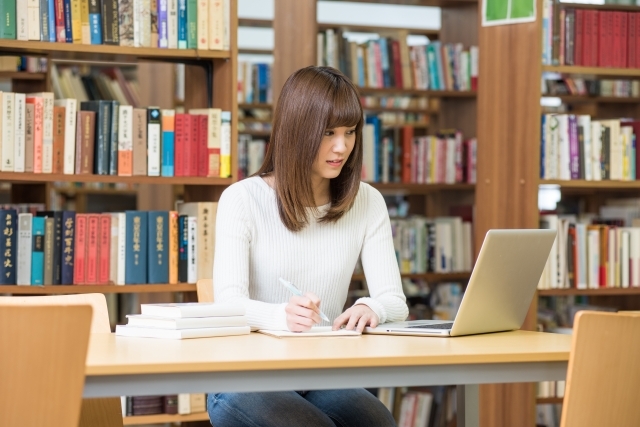「現代文って、どう読めばいいか分からない…」多くの受験生がそう感じているかもしれません。
しかし、共通テストの現代文は、意外と「読んで理解する」能力よりも「情報処理力」を問う性質が強い試験です。つまり、傍線部に関する「情報処理」を確実にすることが、安定して9割を取るための鍵になります。
共通テスト現代文は「傍線部情報処理」形式である
まず押さえておきたい前提が以下。
共通テスト現代文の設問は主に、「傍線部とはどういうことか」「傍線部の理由は何か」の2種類で構成されています。
つまり、「傍線部とはどういうことか=言い換え表現を探せ」「傍線部の理由=言い換え表現を探せ」という形式に帰着します。
要は、傍線部と“等号”で結べる箇所を本文中から探し、選択肢を“書いてある/書いていない”で消していき、最終的に残った選択肢を比較して論点を押さえて正解を決めます。
このように考えると、見た目は複雑な文章でも、「傍線部との対応関係をとる」「選択肢を消す技術を使う」という手順に沿って処理できるようになります。
正答率9割を目指すためのステップ
以下は、1問を解く際の理想的なステップです。これを反復すれば、安定して高得点が狙えます。
1,傍線部と「=(言い換え可能な)」部分を探す
重要なのは、傍線部と意味が等しい/極めて近い文や表現を本文中に探すことです。
多くの場合、傍線部の直前・直後、同じ段落中、あるいは段落をまたいだ隣の文に言い換えや補足説明が書かれています。特に、指示代名詞(「これ」「それ」など)や接続詞(「だから」「つまり」「すなわち」など)が傍線部周辺にある場合、それらを手がかりに「何を指しているか/どういう意味か」を決定します。この時点で、傍線部の意味範囲を「ここかここだ」とある程度絞っておくことが、あとの消去段階で非常に効いてきます。
2,選択肢を「書いてある/書いていない」で消す
次に、傍線部=言い換え表現を探した(またはその候補範囲を定めた)部分を根拠箇所とし、その根拠部分に書いてあることを判断基準として選択肢を消していきます
ポイントは:
「書いてある」とは、文字どおり同じ語句で出てくるだけではなく、言い換え・同義表現・文脈上の説明を含むものを含むということ。
逆に、本文中に記述・論旨として存在していないもの、あるいは一般論・常識で補っているもの、読み手の主観や意見を混ぜ込んでいるものは「書いていない」と見なして消す。
この段階で、たいてい5つの選択肢のうち3つは明確に消せるようになっています。
この消去作業ができないと選択肢が複数残ってしまい、正解を見つけられなくなります。
3,残った2つを比較し、「論点」を見つける
消去段階を経て残るのは、だいたい2つの選択肢です。この2つをただ順番に丁寧に読むだけでは、決め手が見つからないことが多いです。
そこで、2つの選択肢を横並びで比較して「何が違うか(=論点)」を抽出します。
例えば:
因果・理由/結果か
原因の強弱か
範囲の広さか
主語・対象が違うか
時制・条件などの違いか
こうした「情報としての違い」を言語化できれば、「どちらが本文の論旨に近いか」という判断軸が得られます。そして、論点をもとに、再び本文の対応箇所を読み直し、正解を一つに特定します。
5,資料問題・図表問題も同様に処理する
共通テストでは、現代文に資料問題や図表参照問題が混じることがありますが(たとえば第3問)、基本論理は同じです。すなわち:
傍線部や設問語句を資料図表の該当部分と対応させて読む
図表中のデータや言葉を「書いてある/書いていない」で選択肢を消す
残った選択肢で論点を見つけて比較判断する
このように、傍線部情報処理の基本構造を崩さない形で応用すれば、資料問題も突破できます。
なぜこの手順だけで9割を狙えるのか?
「傍線部処理 → 選択肢消去 → 論点比較 → 根拠確認」の流れに従う方法が、なぜ高得点安定化に効くのか、その理由を整理しておきましょう。
1,設問形式が限定されているから
共通テスト現代文は、「傍線部とは何か」「その理由は何か」という設問が中心です。つまり、著者が傍線部で言っていることを他の表現で再現しているか、理由を説明する根拠を尋ねてくるわけです。だから、この手順で解ける設問が大多数を占めるわけです。
2,情報処理試験だから
現代文は、内容の深読みや背景知識で解くのではなく、文章中に与えられた情報から処理する力が試されています。つまり、「読む」と「取る(情報把握)」を最小限のステップで行うことが得点を安定させる道です。
3,選択肢は“相対評価”設計
共通テストは、5つの選択肢の中で「絶対に正しいもの」を尋ねる設計ではなく、「他と比べて最も正しいもの」を選ばせる設計です。したがって、選択肢を比較する能力(論点を出す力)が問われています。この比較判断を飛ばしてはいけません。
4,論点をはっきり意識することで誤りを防ぐ
多くの受験生は、残った選択肢のどちらも一見正しそうに見えるために迷います。しかし、違いを論点化できれば、どちらか一方が本文の趣旨・言葉遣い・文脈と不一致であることがクリアになります。
実践上の注意点・練習法
1,選択肢を△(判断保留)にする勇気を持つ
判断つかない選択肢は、悩む時間を浪費するだけなので、素早く△を打って保留にしましょう。
2,選択肢内を読点ごとに区切って吟味
ひとつの選択肢の中にも複数の要素が混ざっている設計なので、読点で区切ってひとつずつ本文対応を取る視点が重要です。
3,指示代名詞・接続詞に敏感になる
傍線部近傍に「これ」「それ」「だから」「すなわち」などがある場合、それらの指示・接続関係を正確に取らないと正解を逃します。
4,過去問演習で手を動かしながら“型”を身体化する
この手順をただ頭で理解するだけではなく、過去問を解くたびに必ずこの流れ(傍線部対応 → 消去 → 論点 → 根拠)を意識しながら処理するクセをつけてください。
まとめ:シンプルな型を体得しよう
共通テスト現代文で正答率9割を安定して出すためには、以下の型を体得することが最重要です。
傍線部とイコールで結べる箇所を本文中で探す
選択肢を「書いてある/書いていない」で消す
残った2つを比較し、論点を出す
その論点をもとに、本文の根拠箇所を読み直して正解を確定する
この流れさえブレなければ、多少難しい文章が出ても、選択肢処理によって得点を大きく落とすことを防げます。
受験まで残り時間は限られていますが、この型を体に染み込ませる訓練は、短期間でも伸びる可能性があります。人見読解塾では毎年、超短期間の受講であっても正答率9割の生徒さんを輩出しています。
さあ、この手順を毎日反復し、過去問・模試で体得していきましょう!
最後まで走り切って、9割超えをつかみ取ろう!