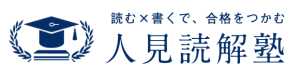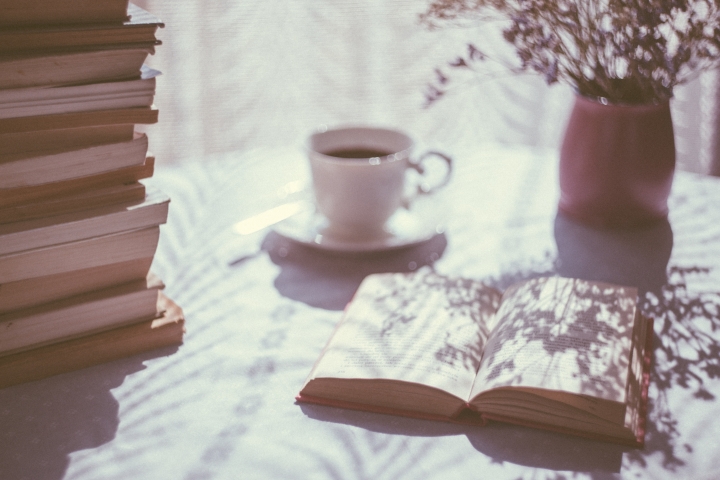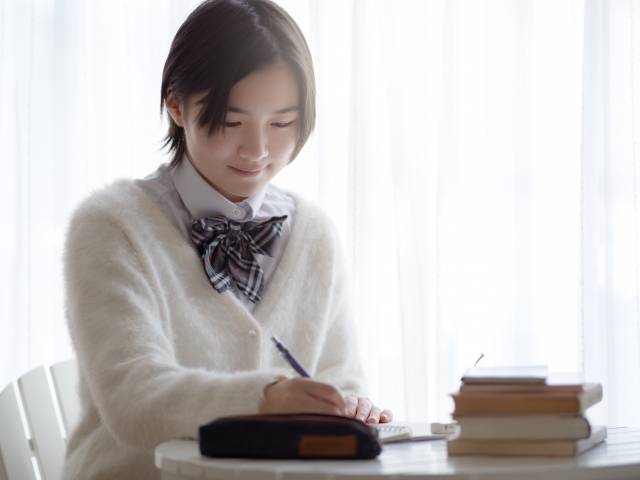人見読解塾の教育 ――評価しないことで、学びは前に進む
総合型選抜、志望理由書、小論文、そして不登校や学び直しの支援において、人見読解塾が一貫して大切にしているのは、
すぐに評価しないこと
答えを急がせないこと
です。
教育が人を止めてしまう瞬間がある
多くの教育現場では、次のような問いが当然のように置かれています。
いつ完成しますか
どれくらいできていますか
正解に近づいていますか
しかし私は、その問いそのものが、人の思考を止めてしまう場面を数多く見てきました。
考えているのに言葉にならない生徒
頑張っているのに筆が進まない受験生
問いを持っているのに、評価されるほど黙ってしまう人
人見読解塾が向き合うのは、
人見読解塾はすぐに評価しません
人見読解塾は、学びを「できた/できない」ですぐに判断することをしません。それは、評価を放棄しているからではありません。
評価の位置を、意図的に後ろへずらしている
それが人見読解塾の教育設計です。
なぜ、評価を遅らせるのか
学びは、次のような循環の中で深まります。
行為する
迷う
立ち止まる
振り返る
もう一度考える
この途中で「良い」「悪い」「正しい」「不十分だ」といった評価が入ると、
思考が縮み
探究が止まり
学びが再開されなくなる
ことがあります。
人見読解塾では、これを経験の早期固定と捉えています。
この考え方は、ジョン・デューイ が示した「教育とは経験の再構成である」という思想にも基づいています。
人見読解塾の学習システム
「成果の代わりに、3つの状態を見る」
人見読解塾では、点数や完成度の代わりに、次の3つの状態を見ています。
1.学びの行為が止まっていないか
小さくても、再び考えようとしているか
同じ場所で思考が止まり続けていないか
2.意味が育ち始めているか
自分の言葉で説明しようとしているか
考えが揺れ、更新されていないか
3.社会とつながり直そうとしているか
他者の視点を取り込もうとしているか
学びを文章や対話として外に出そうとしているか
これらは、成果を競わせるための評価基準ではありません。
学びが前に進める状態にあるかどうかを確認するための観測点です。
「まだ分からない」を否定しません
人見読解塾では、
志望が定まらない
問いが言語化できない
自信が持てない
という状態を、未熟さや失敗とは考えません。
それはむしろ、
深く考えている証拠
次の一歩の手前にいる状態
であることが多いからです。
「まだ分からない」と言える状態を守ること
それが、本当に自分の言葉で書ける志望理由書や小論文につながると人見読解塾は考えています。
人見読解塾が育てたい学び
人見読解塾が目指しているのは、
早く正解を書く力
テンプレートを再現する力
ではありません。
自分の経験を引き受け
問いとして考え
他者に伝えられる言葉へと育てる力
です。
評価は、その力が育った あとで 行えばよい。
人見読解塾は、学びが再び動き出すための時間と構造を守る塾です。
おわりに
評価しないのではなく、急がせない
人見読解塾は、学びを急がせません。
それは、学びを甘やかすためではなく、学びを壊さないためです。
まだ途中にいる人が、安心して考え続けられる場所であること。
それが、人見読解塾の教育です。