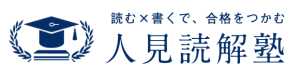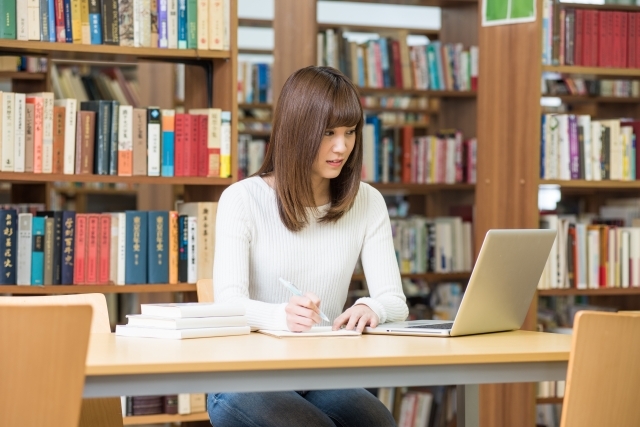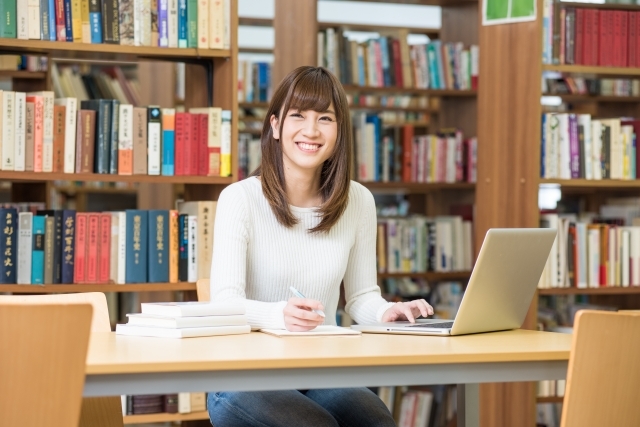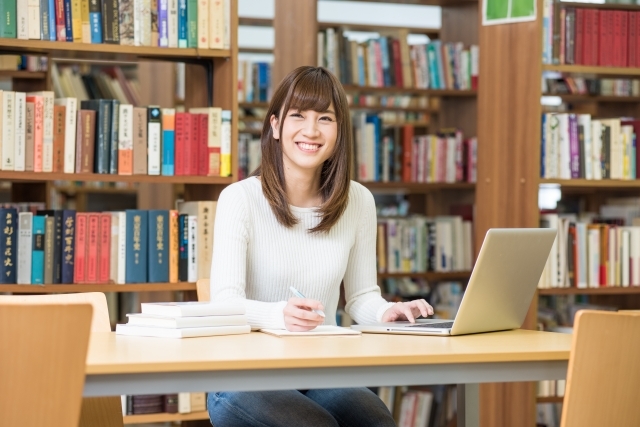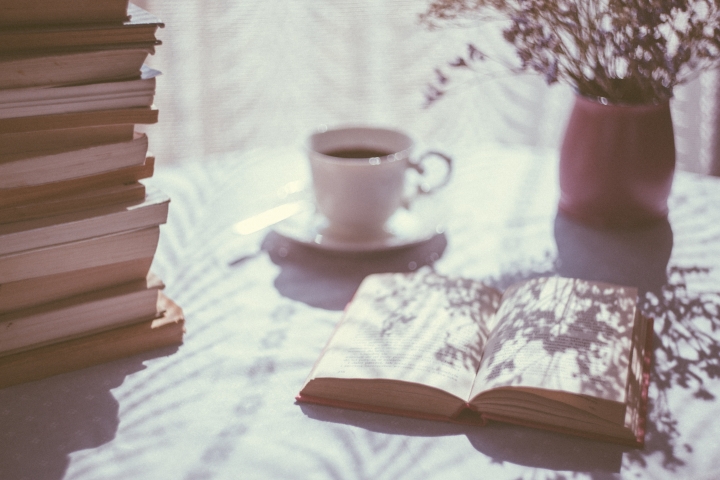卒業論文は大学生活の集大成。けれど「どうやって書き進めればいいのか分からない」と悩む学生は多いです。ここでは、卒論の基本的な書き方ステップ を順序立てて解説します。
1️⃣ 問い(研究課題)を立てる
卒論は「問い」から始まります。「●●とは何か」「なぜ●●は起きるのか」という研究課題を明確にすることで、論文の方向性が定まります。
2️⃣ 主張を明確にする
問いに対して「私はこう考える」という立場=主張をはっきりさせましょう。
主張があいまいだと、根拠も流れも崩れてしまいます。
3️⃣ 根拠を集める
主張を支えるために、文献・データ・事例などを幅広く集めます。
図書館やオンラインデータベースを活用し、信頼できる資料を押さえることが重要です。
4️⃣ アウトライン(構成)を作る
序論―本論―結論の流れを意識して、論理の道筋を整理します。
見出し単位で「何を伝えるか」を明確にすると、書きやすくなります。
5️⃣ 本文を書く
構成に沿って執筆し、必要に応じて修正を加えていきます。
完璧を目指すより、まずは書き出すことが大切です。書きながら精度を高めていきましょう。
✨ 卒論指導の活用
人見読解塾の卒論指導では、このステップを一緒に進めていきます。
テーマ設定・問いの立て方から、アウトライン作成・添削無制限までオンラインで徹底サポート。「卒論が書けない」「卒論テーマが決まらない」という状態から抜け出し、自分の力で卒論を完成させる力を育てます。さあ、一緒にやっていこう!