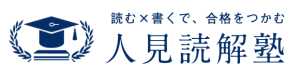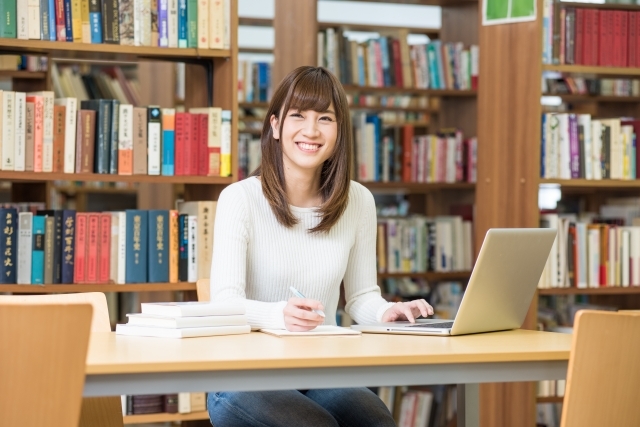暗号を「情報処理」するように読む 共通テストの古文・漢文で高得点を取るには、感覚的な“読解”ではなく、構造に基づいた情報処理が鍵です。試験が求めているのは「古文を味わう力」ではなく、「
文法というルールで暗号を解析する力」です。
つまり古文・漢文は、文学ではなく“データ”として扱われています。古典を情報として読み解く——これこそ、9割突破の核心です。ちなみに現代文も「問題文の内容」ではなく「文法に依拠して構造を読む」問題です。いくら内容を理解しようとしても無理なものは無理です。
👉共通テスト現代文で9割を狙う方法は
こちら
① 文法を「使える形」で覚える
まず押さえるべきは、学校で習う基礎事項。ただし「知っている」ではなく、「使える」状態にすることが重要です。
助動詞の意味と接続
助詞のはたらき(特に「を・に・が・は」)
敬語の区別(尊敬・謙譲・丁寧)
この3点を“知識”から“思考ツール”に変えることで、読解の精度が一気に上がります。
特に主語の省略が多い古文では、助動詞や助詞を手がかりに「誰が何をしているか」を見抜く力が得点を左右します。基礎の精度が高いほど、情報処理のスピードも上がり、正答率9割が見えてきます
② 傍線部を「前後の文脈」で処理する
共通テストの古文・漢文で最も問われるのは、傍線部の“前後”をどう読むかです。本文すべてを訳す必要はありません。正解の根拠は、必ず傍線部の近くにあります。つまり「本文を全部理解する」より、「傍線部周辺を正確に処理する」方が点につながるのです。
傍線の前後に注目し、
主語の変化
敬語の方向
接続助詞による因果関係
会話文や引用の切り替え
これらをスキャンするように読み取る。
それが“古文の情報処理読解”です。
③ 過去問で「出題のクセ」を体に覚え込ませる
共通テストで9割を取る生徒は、例外なく過去問分析をやり込んでいます。文法の暗記だけでは対応できない「出題者の思考パターン」をつかむためです。
特に多いのが次の3パターン。
傍線部の言い換え(内容一致)
心情・理由を問う問題
文体やジャンルによる論理展開の違い
これらは過去問を通じて「型」を覚えるしかありません。人見読解塾では、設問の作り方を“逆算的”に理解し、出題意図そのものを解説します。
👉共通テスト英語9割突破の勉強法もあわせてご覧ください。
④ 古文を“感覚”でなく“論理”で読む古文は「雰囲気で読むもの」と誤解されがちですが、実際はきわめて論理的です。たとえば「〜なりけり」という表現。これは「過去の回想」か「発見の驚き」のどちらかを示します。この違いが取れれば、選択肢の正誤を瞬時に判断できます。つまり、感覚ではなく構造的に読む訓練が合否を分けるのです。
共通テストが測ろうとしているのは、“文学の理解力”ではなく“論理的な再構成力”。
これは、現代文や英語と地続きの「情報処理スキル」です。
⑤ 漢文も「構文処理」でスピード読解
漢文においても、返り点や句形を単なる暗記ではなく“構文情報”として整理することが重要です。「〜者」「〜也」「〜焉」などは文中の構造を示す目印です。これらを正確に読み取れば、論理の骨格が明確になり、スピードも正確性も上がります。
⑥ まとめ:古文・漢文は「情報処理型科目」
古文・漢文で9割を取るための鍵は、暗記ではなく「情報を構造的に扱う思考」です。
助動詞・助詞・敬語を“使える知識”にする
傍線部前後の文脈を処理する
過去問で出題意図のパターンをつかむ
この3つを徹底すれば、誰でも9割を狙えます。
古典を“読む”から“処理する”へ。
それが、共通テストで結果を出す人見読解塾の方法です。
📚 あわせて読みたい「9割を狙うシリーズ」