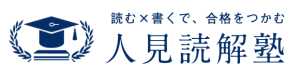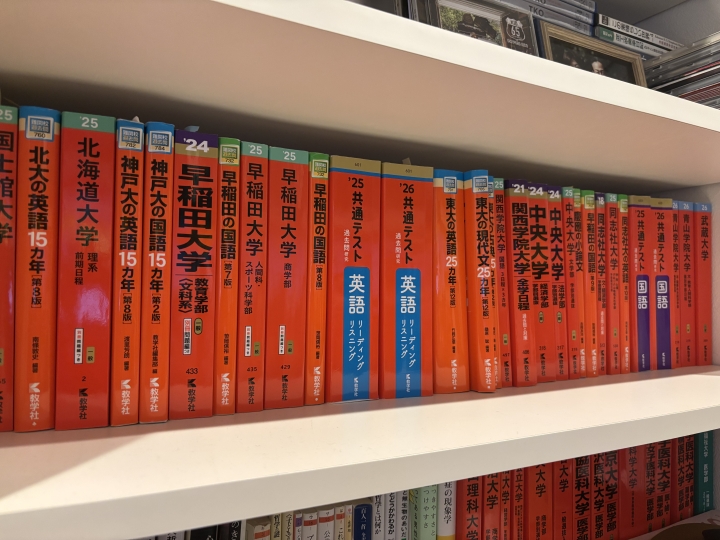早稲田大学の入試現代文は、全国の受験生にとって大きな壁です。その理由は、他大学ではあまり見られない 哲学系の論説文 が高い頻度で出題されることにあります。日常的な常識や教科書的知識だけでは理解できず、筆者の思考の流れを追う「構造読解力」が合否を大きく分けます。
本コラムでは、早稲田現代文の特徴と難しさを整理し、哲学系論説文を突破するための具体的な攻略法を解説します。
早稲田現代文の特徴と難しさ
1,哲学的・抽象的な文章が多い
メルロ=ポンティ、ハイデガー、フランス現代思想など、普段の生活では触れない哲学的な論考が頻出します。
2,常識で推測できない
一般常識や背景知識だけでは本文の主張が見えず、「なんとなく」で選ぶと外れます。本文を忠実に追う読解力が必須です。
3,設問が本文理解を前提にしている
内容一致問題、要約、抜き出し、選択肢問題など、どれも本文の論理を正確に掴まないと解けません。
哲学系論説文を攻略するために必要な力
1. 背景知識を整理する
哲学的な文章を初めて読むと難解に見えますが、典型的なテーマを押さえておくと理解がスムーズになります。
理性と感性の対立や存在論、身体論、言語と意識の関係などの背景知識は「本文の意味をあらかじめ予測する助走」として大きな効果を持ちます。
2. 構造読解力を磨く
段落同士のつながりを「因果関係」「対比」「転換」などで捉え、文章を「骨格」として理解することが重要です。構造を掴めば、設問に対して根拠をはっきり示せるようになります。
3. 設問解法の再現性を高める
正解を「偶然当たる」ではなく、「根拠を追えば必ず正解に至る」形で解く練習が必要です。そのためには、過去問演習と添削を通して、解法のプロセスを定着させることが不可欠です。
具体的な学習ステップ
ステップ1:過去問分析
まずは早稲田の過去問を解き、どのような文章・設問が出るかを把握します。ここで特徴を掴むことで、効率的な対策が可能になります。
ステップ2:背景知識を導入
出題頻度の高い哲学テーマをわかりやすく整理。難解な概念も「要点カード」として簡潔にまとめることで、本文理解を助けます。
ステップ3:構造読解の習得
本文を読みながら段落ごとに「要点・対比・因果・結論」をマークし、論の流れを図式化。骨格を視覚的に理解する訓練をします。
ステップ4:設問解法トレーニング
設問ごとに根拠箇所を探し、本文と選択肢を対応づける練習。本文のどの部分に答えがあるかを必ず明示する習慣を身につけます。
ステップ5:実戦演習と時間配分
制限時間を意識した過去問演習を行い、本番同様の条件で得点力を安定させます。
当塾の指導の流れ
過去問本文を講義形式で解説
設問ごとの解法プロセスを実演
宿題として演習→添削→講評
三者面談やコーチングで学習計画を調整(授業料に含まれています)
完全オンライン・個別指導なので、一人ひとりの弱点に合わせて徹底的に対応します。
受講生の声
「構造読解を学んでから、長い哲学的な文章でも筋道を追えるようになり、設問で迷わなくなりました」
「背景知識を整理してもらったおかげで、抽象的なテーマにも落ち着いて取り組めました」
「過去問演習を繰り返す中で、答案作成の力が安定して伸びたのを実感しました」
まとめ
早稲田大学の現代文、とくに哲学系論説文は、常識や雰囲気では解けません。必要なのは、背景知識の理解 × 構造読解の技術 × 設問解法の再現性。
人見読解塾の「早稲田の哲学系論説文対策講座」では、この三本柱を徹底的に鍛え、合格に直結する読解力を養成します。
👉 まずは無料相談・体験授業からお気軽にお問い合わせください。